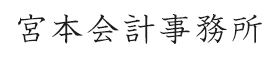貸倒損失の処理は、貸倒引当金と売掛金との振替仕訳でも損金経理とされるか
貸倒損失の処理は、貸倒引当金と売掛金との振替仕訳でも損金経理とされるか
たとえば、当社の取引先の一社の業績が悪化したことで、当期においてその取引先に対する債権の全額が回収できないことが明らかになった場合において、
その取引先に対する債権について前期から損金算入限度額を超過して計上していた貸倒引当金について当期において貸倒損失の確定の経理処理をおこなおうとしたときに、
どのような経理処理で損金経理をすればよいのか、貸倒引当金と売掛金との振替仕訳でもよいかどうかについて、見てみましょう。
前期の経理処理
会計上は、取り立てができない恐れのある債権については、決算日においてその取り立てすることができないと見込まれる金額を控除しなければいけませんので、
たとえ税法上では貸倒引当金に繰り入れることが認められていなくても、その時々の決算日における状況に応じて、
回収不能と見込まれる金額は、貸倒引当金として計上することが求められています。
冒頭の例では、前期から貸倒引当金に計上していますが、
前期において回収不能が見込まれるのであれば、前期において次のように経理処理しなければなりません。
<仕訳例>
貸倒引当金繰入 100 / 貸倒引当金 100
仕訳例としては、このようになります。
ただし、税法上の繰入限度額を超えて貸倒引当金を計上するケースも考えられますので、
その場合には、繰入限度額を超える部分の金額については、申告加算が必要となります。
当期の経理処理
冒頭のように、当期において、当社の取引先に対する債権の全額が回収できないことが明らかになった場合において、
その取引先に対する債権について前期から損金算入限度額を超過して貸倒引当金の計上していたときには、
どのような経理処理とすればよいでしょうか。
経理処理は、つぎのようになるのではないでしょうか。
<仕訳例>
貸倒引当金 100 / 売掛金 100
このように、会計上は、貸倒引当金と売掛金とを”振り替える経理処理”になるものと思われます。
これは、貸倒引当金を計上した前期において、貸倒れの原因がすでに発生していたと考えて、前期に損失を計上済みなので、
当期の損益には前期のことは影響させないという考え方から、この仕訳例のような経理処理が考えられるのです。
もしも前期に計上済みの貸倒引当金を超える貸倒損失となった場合には、その超える部分の金額は、
基本的には、当期に判明した金額であるとして、当期における損失として計上することとなります。
損金経理を考えたときの当期の経理処理
通達においては、回収不能の金銭債権の貸倒れとして、
「その全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において、貸倒れとして損金経理をすることができる。」
とされており、
回収不能が明らかになった事業年度における損金経理の要件があります。
この要件にそのまま従うと、当期においては、つぎのような”両建ての経理処理”が求められると考えます。
<仕訳例>
貸倒損失 100 / 売掛金 100
貸倒引当金 100 / 貸倒引当金戻入益 100
では、先ほどの<仕訳例>のように、
貸倒引当金 100 / 売掛金 100
とする貸倒引当金と売掛金とを”振り替える経理処理”は認められないのでしょうか。
一般的には、両建ての経理処理をすべき
結論としては、通達に忠実にしたがって、”両建ての経理処理”とすべきだと考えます。
つまり、
<仕訳例>
貸倒損失 100 / 売掛金 100
貸倒引当金 100 / 貸倒引当金戻入益 100
のように、元帳に記載すべきだと考えます。
では、
貸倒引当金と売掛金とを”振り替える経理処理”
<仕訳例>
貸倒引当金 100 / 売掛金 100
はどうかといえば、
これでは損金経理の要件は満たしていないと考えます。
ただ、絶対に認められないかといえばそういうわけでもないと思いますが、
一般的ではないのは明らかでしょう。
(絶対にダメというご意見もあるかと思います。)
繰り返しになりますが、通達には忠実にしたがうことが求められると考えます。
それに加えて、決算書上の表示のことも考えれば、
”両建ての経理処理”
<仕訳例>
貸倒損失 100 / 売掛金 100
貸倒引当金 100 / 貸倒引当金戻入益 100
としたうえで、
さらに、決算書の表示上の振替(相殺)処理として、
貸倒引当金戻入益 100 / 貸倒損失 100
を入れておくのが、妥当だと考えます。
ご覧いただきまして誠にありがとうございました。
※この記事は、作成時点の法令や記載者の経験等をもとに概要を記載したものですので、記載内容に相違が生じる可能性があります。
また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。